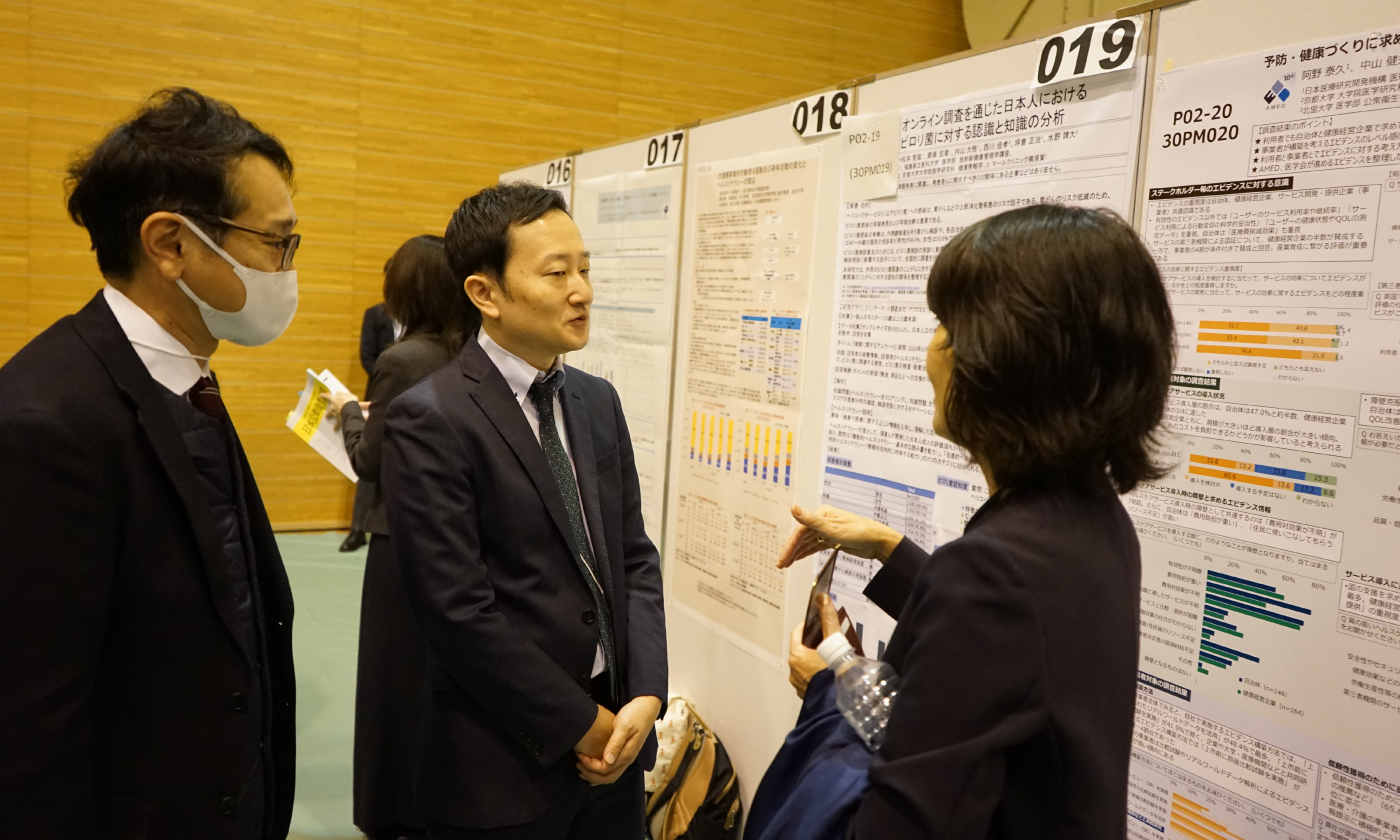デジタル技術を活用した
血圧管理に関する指針づくりの現状と
指針の普及・活用を議論
【第83回日本公衆衛生学会総会】
AMED協賛シンポジウム
「エビデンスに基づいた予防・健康づくりのサービス提供と利用に向けて」レポート
2024年10月29日~31日に札幌コンベンションセンターで開催された第83回日本公衆衛生学会総会。29日に行われたAMED協賛シンポジウム「エビデンスに基づいた予防・健康づくりのサービス提供と利用に向けて」では、AMEDが経済産業省と連携して2022年度から始めた「ヘルスケア社会実装基盤整備事業」の全体像や、日本高血圧学会が中心に取りまとめている「デジタル技術を活用した血圧管理に関する指針」について登壇者がショートプレゼンを行った後、ディスカッションを実施した。

ヘルスケア社会実装基盤整備事業の背景と現状
シンポジウムの座長は、北里大学医学部公衆衛生学教授の堤明純氏(AMEDプログラムオフィサー)と、AMED医療機器・ヘルスケア事業部ヘルスケア研究開発課課長の鈴木友理子氏が務めた。

AMED医療機器・ヘルスケア事業部ヘルスケア研究開発課課長の鈴木友理子氏
最初に登壇したのは、京都大学大学院医学研究科教授の中山健夫氏。AMEDプログラムスーパーバイザーを務めており、その立場からヘルスケア社会実装基盤整備事業の全体像を説明した。

近年、デジタル領域の発展にともない、ヘルスケアアプリなどのサービスが増加している。しかし、予防・健康づくりの領域では、科学的なエビデンスに基づいたサービスの開発や、サービスを選択するための科学的な情報が医薬品や医療機器に比べると整備されていない現状がある。そこで、ヘルスケアサービスの信頼性確保に向けて始まったのが、ヘルスケア社会実装基盤整備事業だ。
同事業では、2022年度よりエビデンスの整理(分野1)と新たな研究手法の開発(分野2)を支援している。分野1においては、関連する疾患分野の医学会が中心となって、予防・健康づくり領域の行動変容介入のエビデンスを整理し、指針の策定を進めており、2024年度末には成果物が公開される。
2022年度の採択課題は、一次予防領域として成人・中年期(高血圧、糖尿病、慢性腎臓病)、老年期(認知症、サルコペニア・フレイル)、職域(メンタルヘルス、女性の健康)を設定。2023年度からは二次・三次予防まで広げ、脂肪肝、循環器、婦人科疾患が対象となっている。
中山氏によると、指針は日本医療機能評価機構医療情報サービス事業Mindsの診療ガイドライン作成マニュアル2020を参照。デジタル技術を活用した行動変容を対象とし、ヘルスケアクエスチョンを立て、推奨度の“行うことを強く推奨する”“行うことを弱く推奨する”に医学会としては重点を置く。十分なエビデンスを得られていないところは、フューチャーリサーチクエスチョンとして記載し、今後の研究に役立てるという。
「指針を使うのは、生活者や患者、企業、自治体、保険者などのサービス利用者と、ヘルスケアサービス事業者(開発者)。例えば、保険者が特定保健指導をする際に、より望ましいヘルスケアアプリを選ぶ一つの取っかかりに指針を使っていただければと思う。また、健康管理のアプリを使っている生活者が数値の変化に気づき、医療者にアプリの結果を見せてケアを進めることも必要になっていくだろう」と中山氏は指針活用の例を挙げた。
分野2においては、予防・健康づくり領域の新たな研究手法の開発を支援する。ヘルスケアサービスの効果を測定する評価指標や尺度の開発、研究デザイン手法の開発が現在進んでおり、得られた成果はサービス事業者が利活用できるように推進していく。
中山氏は、医薬品とヘルスケアアプリの違いについて、「医薬品は市販される前に厳密な検証(治験)を行い、市販後のデータ収集は安全性と適応拡大に主眼を置く。一方でヘルスケアアプリは、市販前は必要最小限の基準をクリアし、市販後のデータ収集で柔軟・迅速に品質向上を継続している。両者の文化の違いを認識しているが、ヘルスケアアプリに対して医薬品と同じような仕組みを作れば、市販後の品質改善が容易ではなくなる」と指摘した。
血圧管理のための適切なデジタル技術の選択に向けて
続いて講演した福岡大学医学部衛生・公衆衛生学主任教授の有馬久富氏は、ヘルスケア社会実装基盤整備事業の指針策定における「デジタル技術を活用した血圧管理に関する指針」の現状を報告した。この指針は、日本高血圧学会が中心となって取りまとめており、有馬氏は指針作成の代表を務めている。
有馬氏はまず、高血圧から脳卒中や心疾患になって亡くなる人が1年間に約17万人(2019年の推計)いることを紹介。生活習慣の改善や薬を使って血圧を下げることで脳卒中などを減らせられるというエビデンスがあるにも関わらず、高血圧患者約4300万人のうち約3100万人は未治療だったりコントロール不良だったりする。これから生産人口が減り、リソースが限られる中、このエビデンスプラクティスギャップを埋めるには、デジタル技術がツールになるのではないかと考えたという。
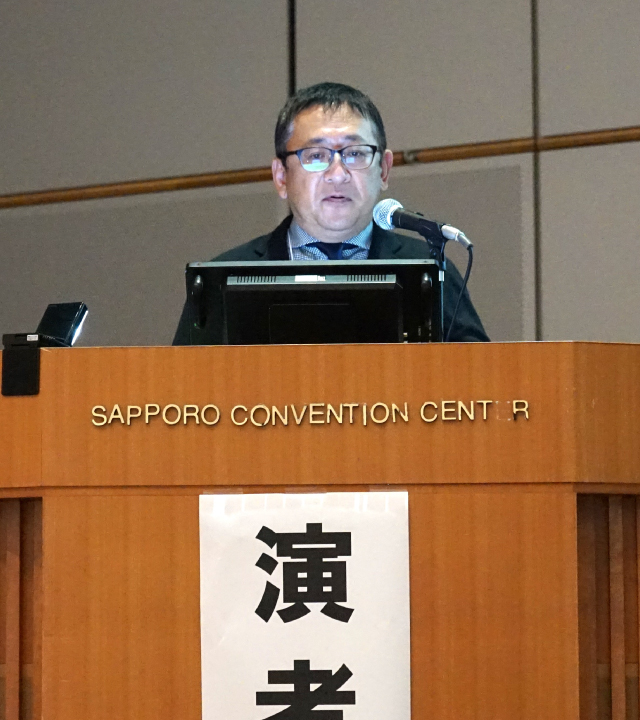
しかし、デジタル技術を活用した血圧低下作用に関するアプリなどにはエビデンスがあるものと、エビデンスがないまま発売されているものとが混在する現状がある。そこで、利用者が血圧管理のための適切なデジタル技術を選択できるように、経済産業省とAMEDの支援を受け「デジタル技術を活用した血圧管理に関する指針」を作ることになった。
有馬氏らは、「デジタル技術は血圧を低下させるか?」という大きなヘルスケアクエスチョンのもと、「血圧測定」「ウェアラブル」「ナトカリ(ナトリウムとカリウムを測るデバイス)」「AI」「アプリ」「遠隔医療・保健指導」の6項目のデジタル技術において、システマティックレビューを実施した。何万もの論文を約60人の医師がスクリーニングし、メタ解析を行ってエビデンスを整理。その結果をもとに、推薦の度合いを「行うことを強く推奨」「行うことを弱く推奨」「行わないことを弱く推奨」「行わないことを強く推奨」「推奨を保留」の5つとし、日本公衆衛生学会や循環器系の学会など関連学会の医師、企業・一般人らも含むメンバーで投票して推奨を決めた。
現在、指針の草案ができ、パブリックコメントを募集している。2025年3月までに指針を公開する予定だ。
有馬氏は講演の中で、この6項目の中から「アプリ」を具体的に紹介。「スマートフォンアプリによる介入は、一般成人において血圧を低下させるか?」というヘルスケアクエスチョンに対して文献検索をし、最終的に76件にメタ解析を行った。その結果、アプリによる介入6ヵ月後の診察室収縮期血圧が約3㎜Hgの低下が認められた。参加者別の血圧変化では、健康な成人は3ヵ月後の収縮期血圧が低下していたが、6ヵ月以降の効果は実証されなかった。高血圧患者では3ヵ月後および6ヵ月後の診察室収縮期血圧が低下したものの、12ヵ月以降はエビデンスが不十分だったという。
ヘルスケアクエスチョンの推奨文(案)は、「成人において、血圧管理を目的としたスマートフォンアプリによる介入を弱く推奨する。ただし、長期間(6ヵ月以降)の効果に関するエビデンスは不十分である」とした。
この指針では、推奨する4種類のスマートフォンアプリも掲載している(個々の研究において有意な低下を認め、かつ日本でダウンロード可能なもの)。「医師の処方のもとに高血圧の治療に用いるCureApp HT、ウェアラブルデバイスと連携したFitbit、高血圧などがある人の重症化予防のための遠隔指導ツールのMystar、栄養指導を行うnBuddy(英語版のみ)の4つで、指針には使いやすさも評価して載せる予定。日本にはこの他にも優れた製品があると思う。開発する企業の皆さんはぜひエビデンスを作っていただき、次に改訂した際にはその製品をリストに載せたい」と有馬氏は期待した。
広く利活用される指針にするために
パネルディスカッションでは、「指針を活用したサービス開発と選択の実装に向けた期待と今後の課題」をテーマに関係者で議論。進行役の堤氏が「策定した指針が、ヘルスケアサービスを提供する事業者や、自治体・健康経営企業らサービスの利用者に広く利活用されるために何が必要だと考えるか、ご意見をいただきたい」と投げ掛けた。
有馬氏は、プレスリリースを行ったり今回のようなシンポジウムを開催したりして周知の機会を増やすとともに、「新しいものがどんどん出てくるため、発信する情報の鮮度を保つことが必要」と語った。
中山氏は、「指針は出して終わりではない」と強調。今回の策定では、ユーザーに十分に話を聞くことができていないため、サービスの開発者やサービスの利用者との対話の場をつくることが大切だとした。
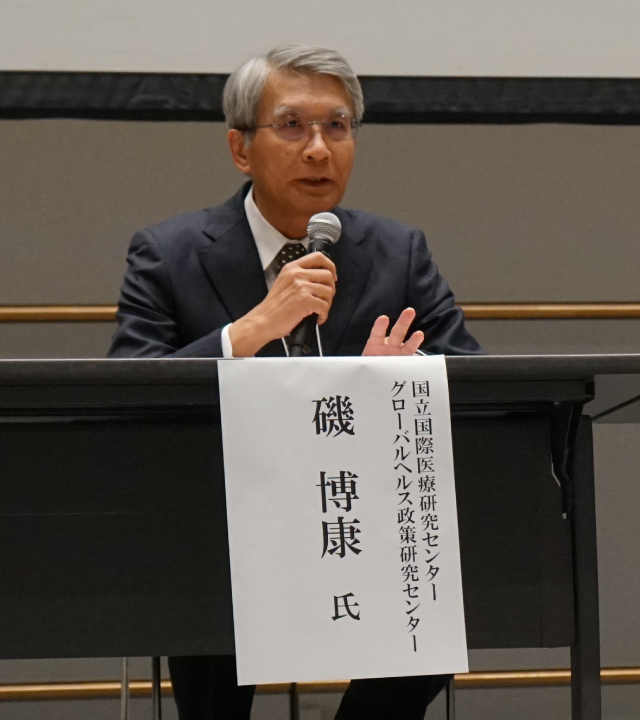
国立国際医療研究センターグローバルヘルス政策研究センター長の磯博康氏は、日本医学会連合の副会長も務めている。今回の指針策定には、日本医学会連合の前会長・門田守人氏から賛同を得て、主要な臨床の学会が指針作成に協力することになったいきさつを明かした。その上で、「ヘルスケア産業のエビデンス構築を補強しながら、利用者が求める現場の声を聞くことが大切。そのためのツールの開発を企業やアカデミアが一緒になって議論し、育てていくことが非常に重要だ」と力を込めた。

経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課課長の橋本泰輔氏は、「経済財政運営と改革の基本方針2024(骨太の方針2024)」に、ヘルスケアサービスにおいてエビデンスに基づくサービスの社会実装を実現するため「AMEDの機能強化を行う」という文言が入ったことに触れた。「今年度できる指針をもとに社会実装していくことが重要で、そのための機能をAMEDに担ってもらうことを政府の方針として示したもの。産業政策を進める経産省として、さまざまな関係者と協力し、国民の予防・健康づくりにしっかりと貢献していきたい」と語った。
この後、会場からの質疑応答に移った。参加者からは「ヘルスケアアプリには優れたものがある一方で、粗悪なものも出ている。この指針を悪用して宣伝に使われることはないのか、危惧する」との声が上がった。
有馬氏は「特にアプリはばらつきがある。今回の指針では日本でダウンロードでき、エビデンスがあるものをリストに掲載しているので、利用者はそこを見て判断していただきたい」、橋本氏は「アプリは基本的にBtoBtoCを経由して使われることが多くなると思う。消費者の間に介在する健康経営企業や保険者などには、リテラシーを持ってもらうことが大事」、中山氏は「開発された経緯やエビデンスの取得の仕方が分かるようなものを、アプリに添付してはどうか」と提案した。
次の質問者は、「エビデンスに基づいた商品を流通させる中で、産学連携をどううまく進めていくのか」と発言。中山氏は「研究者と健康関連の企業では、開発のスピード感や成熟度に差がある。そこはお互いに少しずつ歩み寄り、共通点を探していくことになるだろう」と語った。
磯氏からは橋本氏に、「ヘルスケアのツールに関して、経産省として将来的に認証制度のようなものは考えているのか」という質問があった。橋本氏は「アプリの認証となると、今回の指針策定のように医学会との連携が必要になる。当然、厚生労働省も関わるため、今、認証制度を作るのは難しく、まずは指針の普及に注力したいと思う」と答えた。
最後に中山氏が、「エビデンスに基づくヘルスケアの実装に向けて、分野1、2を進めてきた。改めて思うのは、社会実装が本当のゴールではないということ。その先にあるウェルビーイングや、AMEDが重視する3つのLife(生命、生活、人生)を遠くに見ながら、社会実装を考えることが大事だと思う」と締めくくった。
シンポジウム修了後、「デジタル技術を活用した血圧管理に関する指針」の策定を進める有馬氏と、AMED社会実装基盤整備事業のプログラムスーパーバイザーである中山氏に、それぞれ、指針策定の舞台裏やスーパーバイザーの役割について話していただいた。
●有馬久富氏
今回、私たちが『デジタル技術を活用した血圧管理に関する指針』の作成にあたって苦労したのは、システマティックレビューで論文をセレクトする作業でした。データベースを検索すると、1テーマにつき5000件を超える論文が見つかることが多く、この膨大な量を精査するために、60名の先生方にご協力いただき、人海戦術で進めていきました。
また、各ヘルスケアアプローチに対する推奨度は最終的に委員の投票で決定しましたが、血圧低下を認め、有害事象がない場合でも票が割れることがありました。これはアプリごとに結果が均一でないため、推奨度を一律に出すべきかどうかという議論が生じたためです。その結果、推奨度を一段階下げることになりましたが、指針の解説には機能別の分析なども加えて、より詳細な情報を提供しています。
このように、徹底的に議論を重ねて作り上げた指針ですので、完成した際には広く普及し、啓発活動を進めていければと思っています(談)
●中山健夫氏
AMED事業のプログラムスーパーバイザーの役割は、プロジェクトの採択前には応募案件を評価する立場にありますが、採択後は当該事業が社会実装に向けて効果的に進行するよう、伴走しながら戦略的指導や助言を行う立場になります。目指すべきは、この事業としてのパフォーマンスの最大化です。そして、事業終了後には、その成否が外部に評価されることになります。
私はプログラムスーパーバイザーとして、指針の構成や書き方について注文を出しましたが、先生方には非常に良い形で応えていただきました。指針を作る作業は本当に大変で、だからこそ、作って終わりではなく、その指針が実際に活用されることを目指していきたいと考えています(談)
学会最終日の10月30日には、AMED医療機器・ヘルスケア事業部ヘルスケア研究開発課主幹の阿野泰久氏が、AMEDが2023年度に実施したヘルスケアサービス提供・利用に関する意向調査(詳細はこちら)についてポスター発表を行った。
この調査は、サービス利用者(健康経営企業、健保組合、自治体等)とサービス提供事業者(提供事業者、開発事業者)を対象に、ヘルスケアサービスに関する現状と課題について尋ねたもの。調査結果として、サービス利用者の中でも自治体と健康経営企業では求めているヘルスケアサービスや重視する情報が異なること、サービス提供事業者が取得を考えるエビデンスのレベル感は様々であることなどが明らかになった。ポスター発表の際には、これらのポイントについて質問が相次ぎ、参加者の関心の高さがうかがわれた。