予防・健康づくり領域における
デジタルヘルス活用の指針と今後の展開
【第35回日本疫学会学術総会】
AMED協賛シンポジウム
「デジタルヘルスを活用したヘルスケアの社会実装 ―成果と課題―」レポート
2025年2月12日~14日にかけて高知市文化プラザかるぽーとで開催された第35回日本疫学会学術総会。14日にはAMED協賛シンポジウム、「デジタルヘルスを活用したヘルスケアの社会実装 ―成果と課題―」が行われた。
AMEDが経済産業省と連携して2022年度より開始した「ヘルスケア社会実装基盤整備事業」では、医学会が主導する形で予防・健康づくりに関するエビデンスを整理した指針の策定(分野1)と、新たな研究手法の開発(分野2)が進んでいる。今回のシンポジウムでは、分野1、分野2に関わる医師や研究者らが、これまでの成果や課題を報告。最後は登壇者で活発な意見交換が行われた。

本シンポジウムの座長は、同事業のプログラムスーパーバイザーでもある京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学分野の中山健夫氏と、静岡社会健康医学大学院大学 疫学領域の小島原典子氏が務めた。

静岡社会健康医学大学院大学 疫学領域の小島原典子氏(右)
■ヘルスケア社会実装基盤整備事業の現状
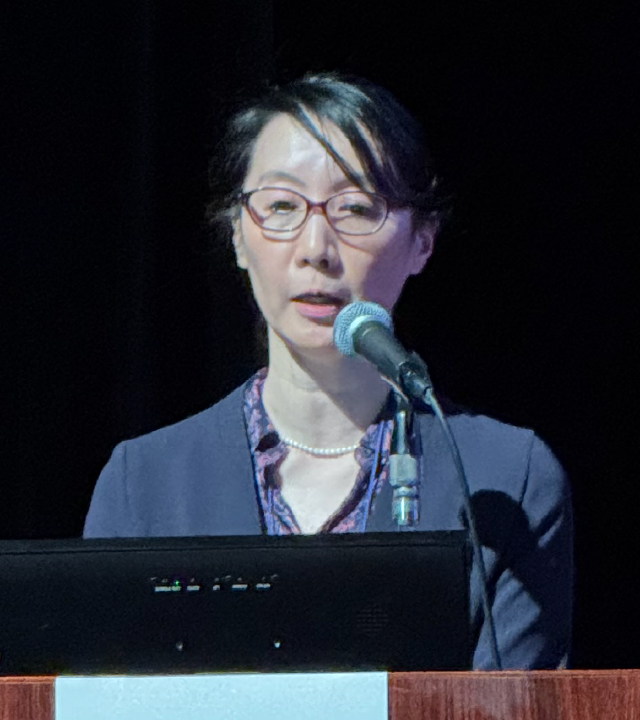
最初に登壇したのは、AMED 医療機器・ヘルスケア事業部ヘルスケア研究開発課の鈴木友理子氏。鈴木氏は、「ヘルスケア社会実装基盤整備事業」について、経済産業省との連携がユニークな点であると述べ、事業内容を説明した。
まず、分野1「予防・健康づくりに関する指針等の策定」について鈴木氏は、第1弾は中年期の課題として高血圧、糖尿病、慢性腎臓病、老年期の課題として認知症、サルコペニア、フレイル、職域関連の課題としてメンタルヘルス、働く女性の健康の7領域に関する指針が策定され、間もなく公開になる旨を報告。これらは、日本医療機能評価機構のの「Minds診療ガイドライン作成マニュアル2020」に基づき、サービス利用者やサービス事業者が活用できるよう、主な行動変容介入に関するエビデンスを整理したものであると説明した。
各領域で歩調を合わせるため、「ヘルスケアクエスチョン」ごとに、「行うことを強く推奨」「行うことを提案」など5段階の推奨度を設定。その中には、「エビデンス不十分のため推奨を保留」という推奨度もあるが、「これは決してネガティブなメッセージではなく、今後の研究が必要であることを示す前向きな位置づけ」と強調した。
次に、分野2では、予防・健康づくりに関するエビデンス構築のために、新たな研究手法の開発が進められており、特に多面的価値評価や、PRO(患者報告アウトカム)、健康関連QOLの評価指標、さらにはリアルワールドデータを活用したエビデンス構築に関する研究が進展していると報告した。
「ヘルスケア社会実装基盤整備事業」は2022年度から始まり、3年が終了しようとしている。いくつかの指針はすでに完成しつつあるが、それで終わりではなく、「指針を維持・更新し普及させるとともに、さらなるエビデンス構築のための研究が欠かせない」と鈴木氏。「今後、疫学者やアカデミアと共同で取り組んでいきたいことがたくさんある」と結んだ。
■デジタルメンタルヘルスに関する指針を報告

産業医科大学産業生態科学研究所 人間工学研究室の榎原毅氏は、「メンタルヘルスに対するデジタルヘルス・テクノロジ予防介入指針」のプロジェクトの研究代表者を務め、同指針の概要を報告した。
デジタルメンタルヘルスに関連する製品やサービスはすでに市場に登場しており、スマートフォンを使ってアルファ波をリアルタイムでモニタリングしたり、顔の映像からストレスを評価するツールなどが存在している。しかし、消費者にとっては、これらが科学的に検証されたエビデンスに基づいているかどうかが不明な現状にある。
そこで、日本産業衛生学会を中心に、日本精神神経学会、日本産業精神保健学会、日本人間工学会、産業保健人間工学会、日本産業ストレス学会、日本疫学会、日本心理学会産業保健心理学研究会が連携し、デジタルメンタルヘルスを活用した予防介入指針の整備を進めている。システマティックレビューやトレンドリサーチのチームが組織され、総勢50人弱の研究者が参加。デジタルメンタルヘルス領域から「ヘルスケアクエスチョン」を27設定した。
一例として、「一般労働者のメンタルヘルス疾患の予防にデジタルヘルスアプリ(認知行動療法)のアプローチは有用か?」というヘルスケアクエスチョンに対しては、約3万7000件の論文をスクリーニングした結果、33件の論文が抽出され、メタアナリシスを実施。その結果、「行うことを提案する」という推奨度になったという。
また、デジタルヘルス・テクノロジーの動向を把握するためのトレンドリサーチでは、今後デジタルメンタルヘルスサービスの応用が期待される11の技術領域(音声・感情解析、運動・身体活動、心拍推定、アバター・メタバースなど)を特定し、過去20年間の論文から各技術の検索キーワードを整理した情報を指針で紹介している。
「音声・感情解析の技術が急速に増加していることが分かり、今後デジタルメンタルヘルス領域での利活用が進むと予想される」と榎原氏。指針は特設の事業サイト「DeLiGHT Project」上で公開する予定で、そこで利用者の声を収集しながら、「常時アップデートしていく運用を目指している」と榎原氏は話した。
■認知症に対する非薬物療法の指針について報告
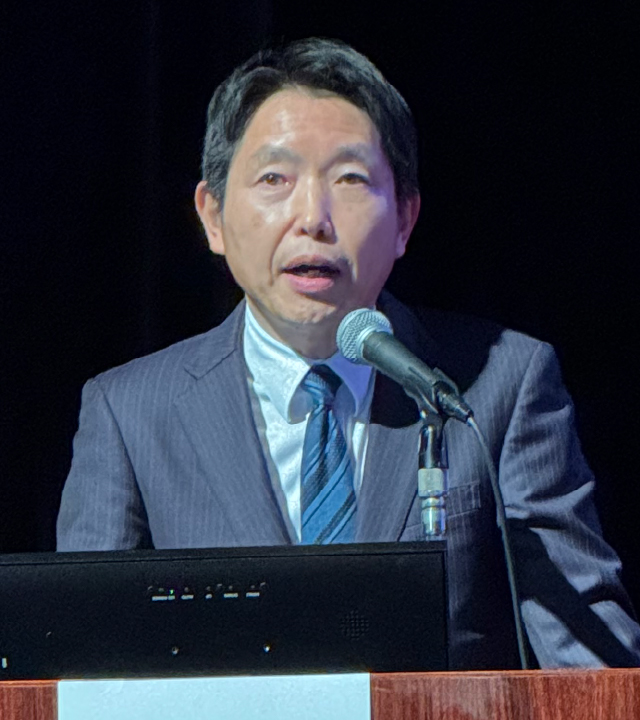
次に登壇したのは、高知大学医学部 神経精神科学講座の數井裕光氏。「ヘルスケアサービス利用者・事業者も使用可能な認知症に対する非薬物療法指針」を作成する委員会の委員長を務めている。
數井氏は、認知症における非薬物療法が注目されている理由について、「アルツハイマー病に対する抗アミロイドβ抗体薬治療が開始されているが、この治療はMCI(軽度認知障害)レベルの人が適用となり、早期であるほどに効果は大きい。そのため、治療対象が認知症からMCIの人にシフトしているが、その対象にならない人もいて非薬物的療法が再注目されている」と指摘。既に、ICTやアプリケーションなど新技術を活用した非薬物療法の商品化がされているが玉石混交の状態という。
そこで、2023年3月、認知症関連6学会(日本認知症学会、日本老年精神医学会、日本老年医学会、日本神経治療学会、日本神経学会、日本精神神経学会)で、「認知症予防に関する民間サービスの開発・発展にあたっての提言」を出した。それを受けて、今回の指針作成もこの6団体が協働し、認知症に対する非薬物療法指針を作成する委員会を組織したという。
指針作成では、まず8種類の療法(運動療法、栄養療法、認知訓練、現実見当識訓練、包括介入<複数の要素を含む統合的なプログラムを実施>、音楽療法、回想療法、精神療法)を選択。これらの療法について、認知機能、日常生活機能(ADL)、運動機能、行動・心理症状、認知症発症のリスク低減に対する効果を検討した文献を集めて内容を吟味し、エビデンスをまとめ推奨度を決めた。ヘルスケアクエスチョンの数は計40個に上った。
例えば、ヘルスケアクエスチョンの「包括介入は、認知機能の向上、維持、低下抑制に有用か?」について、回答は「包括介入は認知症の人の認知機能の向上に有効である。アルツハイマー病の人、軽度認知障害の人、健常高齢者にも有効な可能性がある。」と、推奨度は「行うことを強く推奨する」とした。一方で、「これまでのところ新技術を活用することによって、効果が増強するというエビデンスは乏しい」とも加えた。
なお、本指針では、『行うことを強く推奨する』となったものは他に一つのみ。そのため、近い将来、優先的に研究を実施すべきという観点から、フューチャーリサーチクエスチョンを設定。そこには、「新技術を使って開発を推進してほしいというメッセージを込めた」と數井氏は明かした。
■働く女性の健康づくりにおける多面的価値評価の評価基準を発表
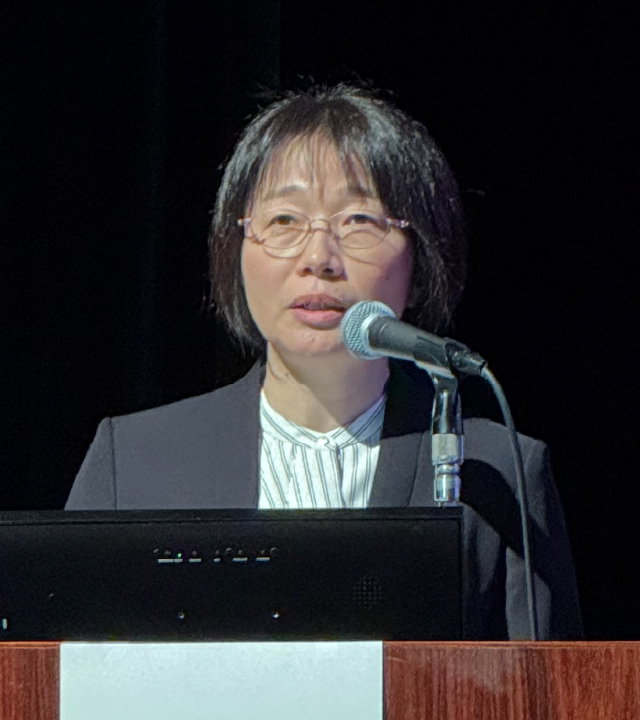
続いて、「働く女性の健康づくりと多面的価値評価」について、東京大学大学院新領域創成科学研究科の齊藤英子氏が発表した。
働く女性にはPMS(月経前症候群)や不妊治療、閉経性の症状などがあり、デジタルヘルス技術を用いての健康づくりが広がっているが、医薬品のように確固とした評価基準がなかったり、市場価格などが曖昧だったりする。「働く女性の健康づくりと多面的価値評価」研究班では、働く女性の健康づくりに資するデジタルヘルス技術の評価尺度づくりをするための研究を進めている。その対象は、健康づくりを目的としたウェアラブルデバイスや健康管理アプリなどの技術や製品とした。
「多面的価値評価」には、経済性評価の価値12要素を示したバリューフラワーをベースに、「生産性」「家族への普及効果」「衡平性」などに着目。働く女性を対象にしたアンケート調査による日本の現状把握、既存技術の有効性評価や費用対効果の検証、海外のデジタルヘルスガイドラインの比較、管理職の女性を対象にしたインタビュー調査による価値基準の発掘などを行った。
これらの研究を踏まえ、働く女性の健康づくりに資するデジタルヘルス技術評価プロトコルを準備している。プロトコルの対象範囲は、働く女性の健康づくりやPMS、妊活、更年期前後症状など女性特有の健康課題への対応を目的としたデジタルヘルス技術や、利用者における行動変容や健康向上を対象とするものに想定。最低限クリアしてほしい「必須評価基準」、推奨レベルの「技術評価基準」、探索レベルの「今後検討が必要な評価基準」の3つに分けた。具体的には、例えば「必須評価基準」では、「安全性が明確である」「プライバシーに十分配慮している」などを示した。「女性の社会参加にとってプラスになるような要素があるか」など女性に特化した項目は「今後検討が必要な評価基準」とした。
齊藤氏は最後に「本研究班では、次の3つを今後の課題として考えている。①ビジネスモデルによって評価基準の優先度が異なる、②ヘルスケアアプリの継続率を高めるための人的介入(産業医や保健師による関与など)をどう評価するか、③デジタルヘルス技術を用いたPMSや更年期対策が労働生産性に与える効果についてエビデンスが乏しく、エビデンスの構築が重要」とまとめた。
■生活習慣病予防のための行動変容継続にどのような条件が必要か
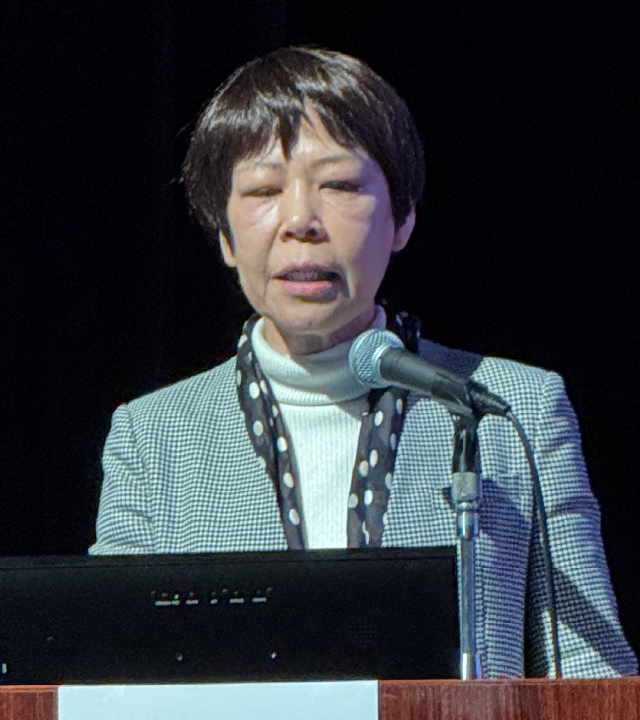
次に登壇したのは、大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学の野口緑氏。生活習慣病予防のための行動変容の継続にスポットを当て、「生活習慣病予防のための行動変容継続に必要な指標開発の試み」を研究している。
この研究開発で目指したのは、「どのような介入が継続的な行動変容に効果的なのか(アプローチ)」「どのような項目について継続的行動変容を行えば生活習慣病予防に効果的か(チェンジアクションプラン)」の2点。これらを統合して、ヘルスケア領域などの研究開発に必要な要件や注意点を整理し、最終的に持続的なヘルスケアサービス環境の構築や継続効果のあるオンラン保健指導研究の発展に資するものにしたいという。
どうすれば行動変容の継続に至るのか、特にオンラインを使った介入を調べるために、5000本あまりの論文をシステマティックレビュー。最終的に残った論文を整理したところ、減量効果が認められたものには、個別のフィードバック、専門的なセルフモニタリング、ネットワーキングといった共通項があった。メタ解析の結果、減量については、オンラインを使った介入は継続的な行動変容に効果があるかもしれないと示された。
行動変容にはどのような項目が必要なのかについては、データベースを使って二十歳からの体重増加と食行動との関係を調べたり、新しい集団に持続血糖測定をして食事などの条件が血糖上昇に関連したりしているかなどを調べた。これらの研究分析から、朝昼夜の食事の中で昼食が最も食後血糖を上昇させたデータが出ており(昼食は夕食に比べエネルギーは低いが炭水化物量が多い)、野口氏は「今後、アプリケーションで介入するアプローチとして、エネルギーの評価ではなく、朝昼夜の食事や炭水化物、脂質、タンパク質のバランスの割合を意識できるような内容が必要ではないか」と提案した。また、HbA1cが5.7を超えると急激に糖尿病発症の確率が上がるため、該当者に生活習慣のアラートメッセージを送るような対応がアプリでできるのではないかと話した。
最後に、行動変容継続のために必要な条件を3つ挙げた。①オンラインアプローチは有効だが効果を上げるためには、個別化されたメッセージやセルフモニタリング、社会的ネットワークのしくみが必要、②なぜ行動修正する必要があるのかをメカニズムで理解できる資料や説明が行動変容継続のモチベーションにつながる可能性がある、③糖尿病、循環器疾患を予防するための生活習慣の修正を目的にしたアプローチには、次の内容を含めることが有効<総エネルギーではなく食事タイプ、タンパク質摂取割合を意識できる表示やメッセージ>、<1年間で3%、あるいは二十歳から10㎏以上体重増加した人は2年間で5㎏の減量目標を設定し持続的に意識できる仕組み>、<朝食欠食、夜食、早食いなどの食習慣を意識化するコンテンツ>。
研究班では、行動変容継続アプローチを網羅したプロトタイプのアプリケーションを開発しており今後、実際の集団に対して介入し、その効果を評価したいという。
■ヘルスケアサービスの社会実装における研究者の役割
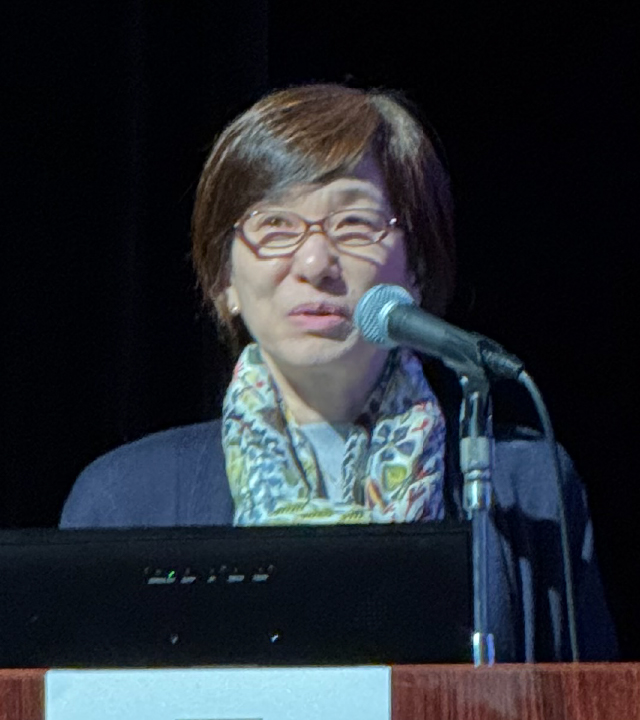
最後に登壇した北海道大学大学院医学研究院 社会医学分野 公衆衛生学教室の玉腰暁子氏からは、AMEDによるヘルスケアサービス提供・利用に関する意向調査(2023年12月上旬~2024年1月上旬)をもとに、ヘルスケアサービスの社会実装における研究者の役割について指定発言があった。
この意向調査は、自治体、健康経営企業、サービス提供事業者を対象に行われたもの。「ヘルスケアサービスの導入を検討するにあたり、サービスの効果についてエビデンスが構築されているかどうかをどの程度重視するか」の問いには、「重視する」が自治体、健康経営企業ともに約5割、サービス提供事業者は7割に上った。エビデンス以外で最も重視するものは、医療費削減効果、サービス利用による行動変容の科学的妥当性、ユーザーのサービス利用率や維持率などが挙げられている。一方で、サービス提供事業者を対象にした問いで「貴社が開発するヘルスケアサービスのエビデンスレベスはどれに当てはまるか」には、比較試験、前後比較試験、事例報告や観察研究に基づく割合が多かった。
このことから玉腰氏は、「ヘルスケアサービスはエビデンスが求められている分野であり、研究者がきちんとした形で研究に関与する余地は十分にあると感じた」と話した。さらに「本日示していただいた指針策定のためのエビデンスの整理は大事だが、それ以上にエビデンスを創出するための研究が必要。どのような研究デザインで行うのか、どんなデータが利用できるのか、どのような効果をもってよしとするのかといったアウトカムを定義することも非常に重要な部分になると思う」と発言した。
■意見交換――指針を活用し産学連携を進めるために
この後は、中山氏の進行のもと、登壇者で意見交換が行われた。中山氏は「指針の利用者を誰だと考えるのか。また、指針の利用者でもあるサービス開発事業者に指針をどう伝えていくのがよいか」と切り出した。
榎原氏は、メンタルヘルス関連の指針は産業保健領域をターゲットにしており、健康保険組合や開発事業者などが使うことを想定しているとし、「サイエンスコミュニケーションの観点から分かりやすい情報発信を重視。私たちの研究課題のウェブサイトではインフォグラフィックやショート動画も含めて発信している」と話した。
數井氏は、認知症に対する非薬物療法の指針の対象者は、いろいろな療法を提供している人や自治体の担当者、健常範囲だが少し物忘れがあるような高齢者、開発企業と考えている。「私たちは1年目の調査で指針の啓発の仕方も調べた。高齢者は若い人のように自分で情報収集することが難しく、信頼できる医療者からの紹介を重視している。そのため医療者への指針の周知も大事」と述べた。
次に中山氏は、研究手法の開発に取り組む中で、産学連携のあり方をどう考えているかを尋ねた。
齊藤氏は、研究者としてはエビデンスをしっかりと取ることが大前提とした上で、「実際にどこまで測定することが現実的なのかを、プロダクトの開発のデザイン期からしっかりと助言していく。どういうデータを取っていけば生産性損失の回避を客観的に測定できるのか、研究者は企業と一緒に走りながらデザインしていくことが求められていると思う」と話した。
野口氏は、企業との連携は極めて重要としつつ、「共同研究していく中で企業の一番大きな関心事は、どれくらいの利用者がいて、どれくらいのマネタイズを想定できるか。しかし、特に行動変容はいろいろな要因が絡み合って成果につながるため特定の項目に限定できず、研究手法が複雑になる。企業がそうした成果を待ってくれるのかどうかが難しいところ」と課題を述べた。
中山氏は、「企業と研究者は、スピード感や何を大事にしているかも異なり産学連携は簡単ではない。これまでも異文化コミュニケーションの連続だったが、さらにディスカッションが必要だと感じている。いろいろな知恵を持ち寄って、ヘルスケア社会実装基盤整備事業を進めていきたい」と締めくくった。
