予防・健康づくりにおける新たな
ヘルスケアサービス創出に向けた実践を報告
AMED・日本高血圧学会 合同シンポジウム
「通信デバイスを用いた高血圧・生活習慣病 評価」レポート
2024年10月12~14日に福岡国際会議場で開催された第46回日本高血圧学会総会。13日の日本医療研究開発機構(AMED)と日本高血圧学会(JSH)合同シンポジウムでは、「通信デバイスを用いた高血圧・生活習慣病 評価」をテーマに、先駆的な取り組みを行っている医師や開発者らが実践報告した。また、経済産業省とAMEDからは、予防・健康づくりにおける新たなヘルスケアサービス創出に向けたビジョンが示され、多くの参加者が熱心に聞き入った。
シンポジウムの座長は、聖路加国際病院 循環器内科の水野篤氏と横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学の田村功一氏が務めた。
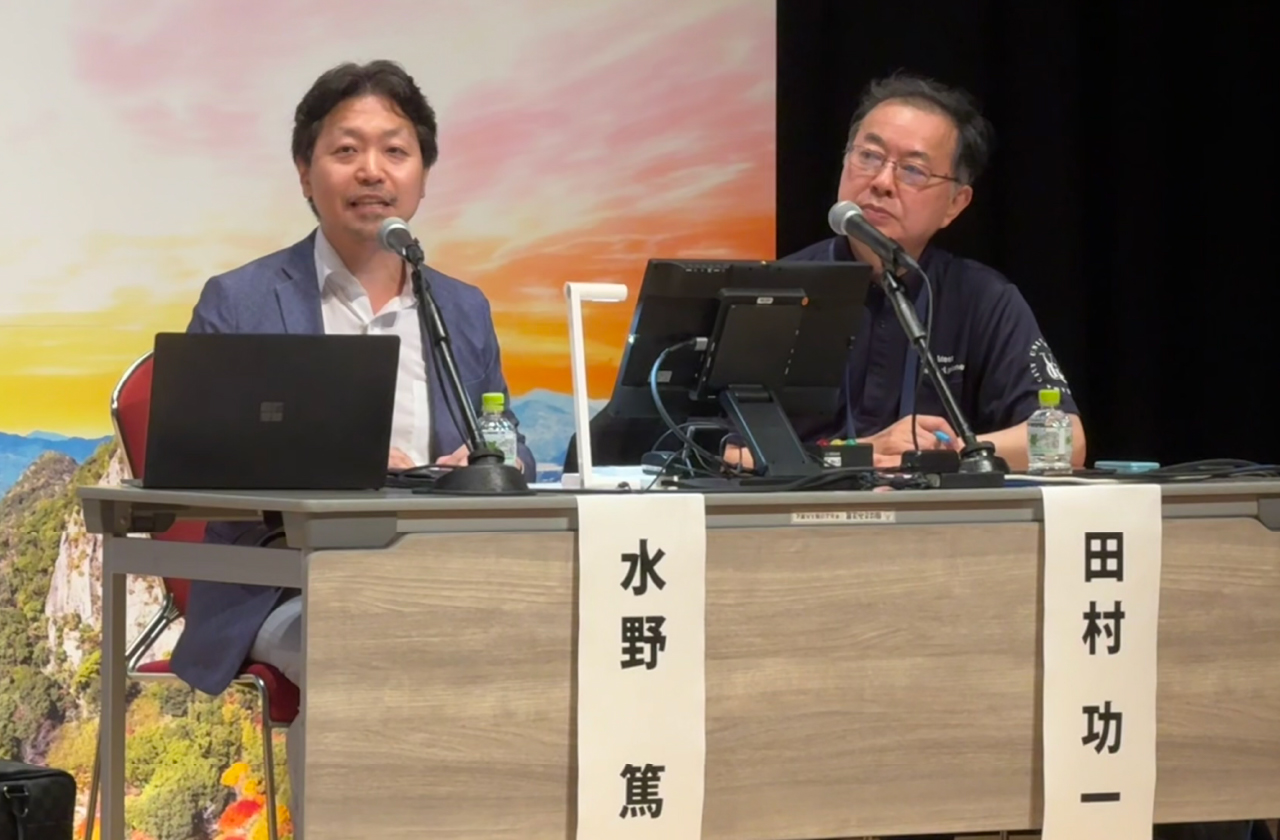
経産省が取り組むPHR活用価値の実証とは?
最初に登壇したのは、経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課の室紗貴氏。経産省が推進しているPHR(パーソナルヘルスレコード)を活用した新たなサービスの創出を中心に説明した。
デジタル技術の発展などにより、PHRを基盤とする製品やサービスが急速に普及する中、経産省では、公的インフラとしての制度整備と、PHR事業者団体を中心とする民間事業者との連携による環境整備を進めている。その一環として現在、国民が実感できる価値あるサービスの創出を目的に、医療現場と日常生活でのユースケース(活用事例)について、実証事業を展開しているという。
これまでに6つの課題を採択。例えば、医療現場でのPHR活用については、高血圧や糖尿病などで通院治療中の患者のPHRデータを医療機関と連携して、自己管理や療養計画の策定に役立てもらうといった取り組みを実施している。「これらの実証事業を通じて、患者、医療者双方の視点でのPHR活用の有用性を検証し、新たなサービス創出につなげたい」と、室氏は今後のビジョンを語った。
続けて室氏は、予防・健康づくりにおける安心・安全なサービスの提供に向けたエビデンス構築の開発支援を、AMEDと連携して実施することにも触れた。AMEDが2022年度から進める「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(ヘルスケア社会実装基盤整備事業)」を通じて、医学会がヘルスケアサービスのエビデンスを整理した「指針」を策定する活動を支援している。
この医学会による「指針」は現在、一次予防として高血圧、糖尿病、慢性腎臓病など7つの疾患領域、二次・三次予防として脂肪肝関連疾患など3つの健康課題を対象にしており、2024年度中に一次予防領域の7指針が公開される予定だ。これを踏まえ、室氏は「指針を活用した製品やサービスが開発されることを促進していきたい」とコメント。2025年度からは「予防・健康づくりの社会実装加速化事業」を新たに立ち上げ、指針の管理・更新、適切な利用に向けた体制整備、アカデミア人材と事業者のマッチングなどを考えていることも明らかにした。

尿ナトリウム・カリウム簡易測定機器の開発と精度検証結果を報告
次に登壇したのは、スタートアップ企業である株式会社ファーストスクリーニングの浅井開氏。同社は非侵襲センサーの開発およびバイタルデータの収集・管理を行っており、開発した尿ナトリウム・カリウム濃度簡易測定機器「P2 Scan ナトカリ」の妥当性についての検証結果を報告した。
「P2 Scan ナトカリ」は、測定器とイオン電極法を使ったセンサーで構成されている。センサーを測定器に差し込み、センサーの先端に尿をかけて20秒ほど待つだけで測定が終わり、結果が測定器の液晶画面に表示される。使用後は、そのまま可燃ゴミとして捨てることができる。また、データはスマートフォンにアップロードでき、同社のサーバーで一元管理される。
浅井氏によると、このシステムを使って、病院で採取された尿検体を使い、精度検証を行ったところ、尿ナトリウム・カリウム濃度やその比(ナトカリ比)おいて、簡易な測定デバイスとして許容できる精度が得られたという。「センサーシグナルのばらつきが大きいなどの課題はあるが、その原因はわかっており、現在改善に取り組んでいる」と浅井氏。「生活習慣病の管理料を算定するための療養指導計画書にも使えるのではないかと考えている」と述べ、今後の展望に期待を寄せた。

スマートフォンアプリ等を使った遠隔医療・保健指導による血圧管理のエビデンスを報告
3番目に登壇した琉球大学 グローバル教育支援機構保健管理部門の崎間敦氏は、AMED「ヘルスケア社会実装基盤整備事業」で進める医学会発「指針」の策定に携わっている立場から、講演した。
崎間氏は、日本高血圧学会が中心となって取りまとめている「デジタル技術を活用した血圧管理に関する指針」の分担研究者の一人。医学会発「指針」は、専門医による組織が、ヘルスケア課題の主な介入方法について、世界中の研究結果を収集・評価し、質の高いエビデンスを基に推奨度を示したもの。例えば、高血圧の領域では「ヘルスケアアプリを用いた血圧管理は成人の血圧低下に効果があるか?」という「ヘルスケアクエスチョン」を設定し、エビデンスを精査して推奨度を5段階で評価している。
崎間氏が担当したのは、ヘルスケアクエスチョン⑥「スマートフォンアプリやショートメッセージなどのデジタル技術を活用した遠隔医療・保健指導は、成人の血圧に有益な効果をもたらすか?」について。そこで実施したシステマティックレビューの結果を報告した。
崎間氏らのチームは、レビューを通じて、18歳以上を対象として、スマートフォンアプリやショートメッセージサービスなどのデジタル技術を活用した遠隔医療・保健指導群(多くは対面での診療と併用)と、標準的なヘルスケア群の血圧変化を比較したランダム化比較試験(RCT)117件と準 RCT 1 件の計 68,677 人を含む 117文献を抽出。このうち 38 件を対象にメタ解析を行った結果、デジタル技術を活用した遠隔医療・保健指導における介入3カ月後の診察室収縮期血圧は、3.21㎜Hg有意に低下していた。介入期間を3カ月、6カ月、12カ月、12カ月以上で解析しても、同等の血圧量の変化が見られた。介入様式別(スマートフォンアプリ、テキストメッセージ、ウェブ)や研究実施施設タイプ別(医療施設、非医療施設)でも、デジタル技術を活用した遠隔医療・保健指導介入による降圧効果は有意であった。なお、介入によって有害事象を増加させることはなかった。
ただし、崎間氏は「研究間で異質性の高さが認められ、介入群の多くが対面診療とデジタル技術導入のハイブリッド型だったことや、長期介入の効果のエビデンスが乏しかったことが課題であり、これらについては今後の検討を要する」と述べ、発表を締めくくった。

家庭血圧計を活用した心房細動の早期発見とその可能性
自治医科大学 循環器内科学の甲谷友幸氏は、家庭血圧計を用いた心房細動の早期発見について報告した。
甲谷氏らは、心房細動を早期に発見するために家庭血圧計に着目。脈波のばらつきを利用して不規則脈波(IHB)を検知するアルゴリズムを確立した。PHRサービスを提供するWelbyの生活習慣病管理ツール「マイカルテ」にIHB管理機能をリンクさせ、患者が登録することでIHBの発現状況を医師が確認できる。データはBluetoothでクラウドに送信されるため、患者は手帳に記録する手間を省ける。実際に、患者の異常な発現状況に気づき、IHBを見つけて心房細動を診断し、治療を行ったケースもあるという。
「心原性脳梗塞で入院した患者の約46%は、心房細動が診断されていないという報告がある。症状があれば早めに病院にかかれるが、症状のない心房細動を見つけることが非常に重要になる」と甲谷氏。また、高血圧の人は脳卒中になりやすい点を挙げた上で、「高血圧患者は基本的に家庭血圧計を持っており、家庭血圧計を使うことはノーリスクで低コスト。血圧コントロールをしながら、心房細動を発見し、抗凝固療法で治療できれば、1人でも多くの命を救えるのではないかと考えている」と結んだ。

充電不要の活動量計と遠隔体調管理システムで健康管理を支援
次に登壇したのは、ウェルエイジングクリニック南青山の青木晃氏。自身が開発に関わり、健康支援を行う企業のメディロムが作ったヘルスケアアプリ「Lav」と、充電不要の活動量計「MOTHER」について発表した。
青木氏は、生活習慣病の外来診療をしていた際、受診後にうな丼を食べる患者がいるなど、適切な生活習慣を継続させることの難しさを実感していた。その後、SNSの普及により、家族や友人とのつながりが容易になり、青木氏自身も人とのやりとりで運動習慣が継続したことから、アプリで行動変容が起こせるのではないかと考え、健康情報管理ツール「Lav」の開発を思いついたという。
「Lav」は、ユーザーと管理栄養士や理学療法士などのコーチが一対一でつながり、チャット機能を通じてメッセージを届け、毎日コーチングを行う仕組みである。歩数や睡眠時間、体重などのデータと食事の写真を使って指導する。このアプリは、自由診療のクリニックや健保組合の特定保健指導プログラムなどで導入されている。
「MOTHER」は、アメリカのMatrix Industries社と共同開発した充電不要の活動量計で、ブレスレット型をしており、体温で発電するため、日々のデータを失うことなく計測し続けることができる。歩数や睡眠、体表温、心拍数などを計測でき、スコアリングして点数で示す。SDK(Software Development Kit。ソフトウェア開発キット)を開放することでさまざまな企業でデータの共有ができるようにしているという。
「このMOTHERに遠隔体調管理システム“REMONY”を同期させることで、データをリアルタイムで一元管理できることから、高齢者の見守りやドライバーの健康管理などに役立てられている」と青木氏。神奈川県の介護ロボット導入支援事業補助金の対象機器として認定されている実績も明らかにした。

オンライン診療支援で高血圧患者の管理をサポート
続いて、一般社団法人テレメディーズの谷田部淳一氏は、福島県会津若松市で実施している高血圧患者へのオンライン診療支援事業について説明した。
2016年に、患者に対して通院するストレスを調査したところ、病院での待ち時間が長い、話を長く聞いてもらえない、調剤薬局でも待たされるなどの声があった。そこで、一般社団法人テレメディーズを立ち上げ、スマホ1台で完結する生活習慣病特化のオンライン診療サービスを開発したという。インターネットを活用したテレモニタリングとテレメディシンを組み合わせており、患者が自宅で通信機能付き血圧計を使用して家庭血圧を測定すると、データがサーバー上に蓄積され、それを看護師などの専門スタッフがモニタリング・分析し、患者にアドバイスをフィードバックする。医師による診療もビデオ通話で行われ、治療結果に基づき、後日、薬が郵送で届くという仕組みだ。基本利用料は月額1,980円と定額制で、診療・薬代は都度請求の保険適用となっている。
「患者が血圧の数値を手書きで記録すると、数値の傾向が分かりにくいが、パソコンにデータが表示されることで月ごとの推移が把握でき、より精密な診療が可能になる」と谷田部氏。医師は画面で血圧のデータを確認し、数値が高ければ治療を強化したり、季節による変動があれば適切なアドバイスを行ったりできる。また、一般的に高血圧患者は初診から1年後には半数が通院を続けていないが、当サービスの利用者は半年後でも約90%が継続しているという。
さらに、地方ではスマートフォンを持っていない高齢者が多いため、コンセントに差すだけでインターネット通信できるゲートウェイ使って、患者のバイタルサインを見守る臨床試験を行っている。「このシステムでは、送られたデータをもとに、例えば1週間で体重が3㎏増加した場合、主治医と患者が連絡を取り合い、適切な対策を講じることができる」と、谷田部氏はメリットを語った。

医学会発「指針」の中味とAMEDが進めるエビデンス取得支援の今後
最後は、AMED 医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課の阿野泰久氏が登壇。まずは、現在、AMEDのヘルスケア社会実装基盤整備事業で行われている、医学会による「指針」の中味の一例を紹介した。
阿野氏は、サルコペニア・フレイルと高血圧、糖尿病予防のためのヘルスケアアプローチについて、各指針ではそれぞれどんなヘルスケアクエスチョンを設定しているかを説明。その上で、例えばフレイルやサルコペニアのリスクの高い高齢者に対するデジタルヘルスサービスを用いた介入の推奨度は「弱く推奨する(提案する)」となる見込みであることを明らかにした。
続いて阿野氏は、指針の普及活動に先立ち、サービス利用者(健康経営企業、健保組合、自治体等)とサービス提供事業者(提供事業者、開発事業者)を対象に、ヘルスケアサービスに関する現状と課題ついて調査を実施した旨を報告し、その結果も披露した。
調査によると、サービス導入時に利用者が重視する項目は、「サービスの効果を示すエビデンス」と「導入後の利用率や継続率」が多く、次いで「情報セキュリティ」と「ユーザーインターフェース(使いやすさ、分かりやすさ)」が挙げられた。自治体では「他地区での導入実績」を重視する傾向が見られた。
また、エビデンスの重要性は自治体、健康経営企業、サービス提供企業の共通認識であった。 有効性のエビデンス以外では三者とも「ユーザーのサービス利用率や継続率」「サービス利用による行動変容の科学的妥当性」「ユーザーの健康状態やQOLの測定データ」を重視。自治体は他に「医療費削減効果」を重視する割合が高かった。
サービス提供事業者のエビデンス構築方法としては、対照群を置いた「比較試験」が3割を占めたが、「前後比較試験やエキスパートオピニオンに基づくと答える事業者もあり、エビデンスのあるべき姿の整備が今後必要だと考える」と阿野氏は述べた。
2024年度には7疾患領域に関する指針と、同時に進めている新たな研究デザインの評価方法に関する成果物が示される見込み。これを踏まえてAMEDは、来年度以降、策定された指針と研究手法を基に、ヘルスケアサービス事業者へのエビデンス取得支援を検討していくことを予定している。阿野氏は「エビデンスの取得だけでなく、事業化の計画や利用者が求めるエビデンスの特定、最終的には社会実装できるように支援していきたい」と展望を語った。
